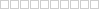EJU线下全科辅导班|日语EJU原创文章写作指导
发布日期:2025-05-09 作者:任老师 文章来源:未知 浏览次数:次
EJU线下全科辅导班|日语EJU原创文章写作指导 近年、グローバル化が加速する中、日本でも多文化共生社会の実現が重要な課題となっている。特に言語の役割は、異文化間の理解を深める上で極めて重要だと考える。本稿では、言語が多文化共生にどのように貢献できるか、三つの観点から論じたい。
第一に、言語学習は相互理解の第一歩である。例えば、在日外国人が日本語を学ぶことで、地域社会とのコミュニケーションが可能になる。逆に日本人が外国語や異文化を学ぶことで、相手の立場を理解する姿勢が生まれる。2020年の総務省調査によると、日本語教室に通う外国人居住者の約70%が「地域とのつながりが増えた」と回答している。このデータが示すように、言語は人間関係を構築する重要なツールなのである。
第二に、言語の多様性が社会を豊かにするという点だ。都心部を中心に、多言語表記の公共施設や観光案内が増加している。これは外国人にとって便利なだけでなく、日本人にとっても異文化に触れる機会となる。私自身、駅の多言語放送を聞いて外国の響きに興味を持ち、国際交流イベントに参加するきっかけになった。この経験から、日常的な言語接触が視野を広げると実感している。
しかし課題も存在する。特に言語格差の問題である。日本語が堪能な外国人とそうでない人の間で、就労機会や社会保障情報のアクセスに差が生じている。これを解決するためには、行政による多言語支援の充実と共に、私たち一人一人が「やさしい日本語」を使うなどの配慮が必要だろう。
結論として、多文化共生社会では、言語が「壁」ではなく「橋」となることが不可欠である。異なる背景を持つ人々が互いの言語と文化を尊重し合うことで、真の共生が実現すると信じる。私たちにできる第一歩は、まず身近な外国人に笑顔で声をかけることから始まるのではないだろうか。
(798字)
構成のポイント:
EJU頻出テーマ:グローバル化・多文化共生を扱い、社会性のある内容
論理展開:主張→具体例→データ→自身の経験→課題→解決策の流れ
表現技法:
接続詞:「第一に」「しかし」「結論として」で論理明示
データ引用:総務省調査で説得力向上
比喩表現:「壁ではなく橋」などの印象的な表現
語彙レベル:
EJU线下全科辅导班|日语EJU原创文章写作指导 N2~N1レベルの語彙(「加速する」「多様性」「堪能な」等)を適度に散りばめつつ、全体の8割をN3レベルで構成。

一起来交流一下吧~
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!